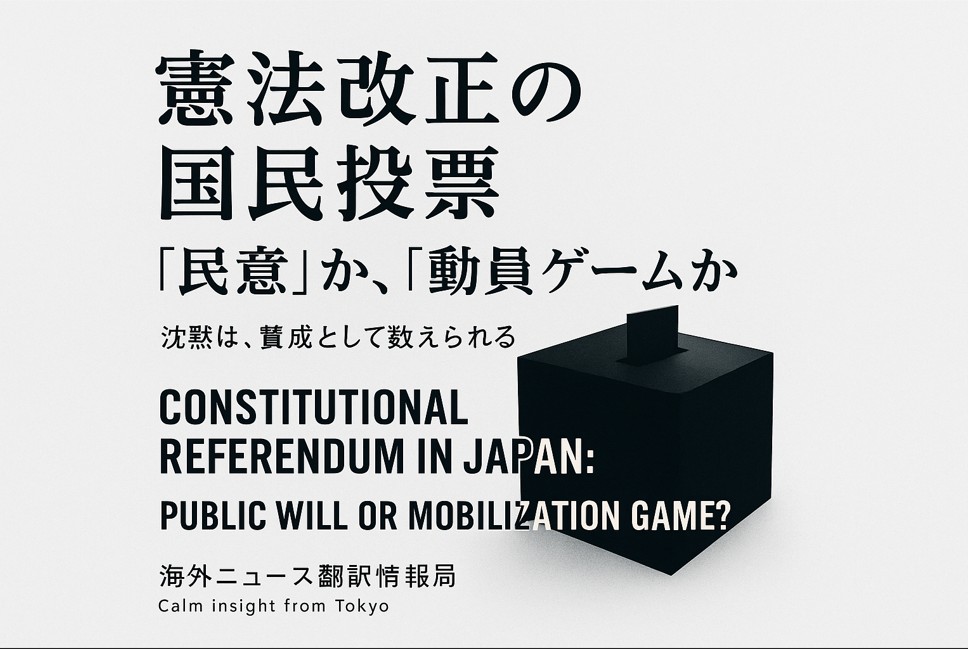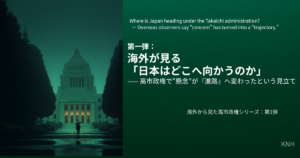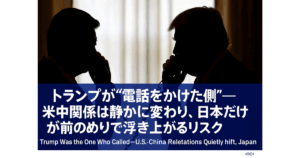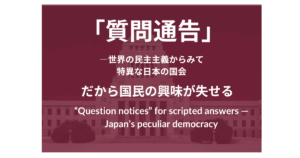憲法改正の国民投票――「民意」か、「動員ゲーム」か
表向きは「国民に問う」民主的手続き。しかし、その制度をよく見ると、沈黙が切り捨てられ、動員力のある側が勝てる仕組みが見えてくる。さらに、その裏側で“ネット動員のインフラ”も静かに整えられている。
📰 導入
11月4日の衆議院本会議で、高市早苗首相は憲法改正についてこう述べました。
「改正案を発議し、少しでも早く憲法改正の賛否を問う国民投票が行われる環境を作っていけるよう、粘り強く全力で取り組んでいく覚悟だ」
この発言に対し、X(旧Twitter)で まりなちゃん(@t2PrW6hArJWQR5S) が制度面から非常に重要な指摘をしています。
なぜ高市が国民投票をゴリ押しするか分かる?国民投票は有権者ではなく、投票者の過半数で決定する「絶対得票率制」だからです。組織票と莫大な宣伝費を持つ改憲派が必ず勝つ。国民投票をすれば100%改憲できるから、国民投票をやろうとしているのです。https://t.co/E6x50clLfO
— まりなちゃん (@t2PrW6hArJWQR5S) November 5, 2025
この投稿のポイントは、「日本の国民投票は有権者全体ではなく、実際に投票した人の“過半数”で決まってしまう」という制度の本質を突いたことです。棄権が多ければ多いほど、組織票・固定票の影響力が大きくなる――この構造を理解しているかどうかで、憲法改正の見え方はまったく変わってきます。
産経新聞の報道は「国民的議論を深める」「環境作りに全力で」といった美しい表現で包んでいますが、実際には「早く国民投票を実施したい」「そのための空気を整えたい」という政治的意図が透けて見えます。
つまり、
- 表向き:民主的手続きを重んじるポーズ
- 実 質:低投票率でも勝てる“動員戦略”の準備
という構図です。以下、この構図を順にほどいていきます。
■ 「絶対得票制」というカラクリ
日本の憲法改正の国民投票は、「有権者の過半数」ではなく、あくまで「投票者の過半数」で決まります。ここが最大のポイントです。
たとえば有権者が1億人いても、投票に行ったのが4,000万人なら、その4,000万人のうち過半数が賛成すれば改憲は成立します。残り6,000万人の沈黙は、最初からカウントされません。これは、棄権が“反対”にも“保留”にもならず、まるごと消えてしまう仕組みだということです。
この構造では、投票率が下がれば下がるほど、組織的に人を動かせる陣営が有利になります。宗教団体、業界団体、特定の政治勢力――こうした「呼びかければ必ず来る」支持層を持っている側です。
だからこそ、「国民投票をすれば100%改憲できるから、やろうとしている」という見立ては、決して誇張ではありません。勝てるフィールドで勝負しようとしているだけです。
さらに問題なのは、日本の国民投票法には「最低投票率」の規定がないことです。投票率が30%でも、そこでの過半数が賛成すれば成立してしまう。これでは「国民の総意」ではなく「組織票の力学」で憲法が書き換わるリスクがあります。
■民主主義の装いをまとった“動員戦”
国民投票は一見すると「国民に直接問う」という民主主義の極みのように見えます。しかし、制度の実際の振る舞いを見ると、それは「どれだけ味方を会場に連れてこられるか」を競う動員ゲームにもなり得るのです。
高市首相が口にする「環境づくり」という言葉も、聞こえは柔らかいですが、現実には「改憲が自然だ」と思わせる空気を事前に広げることを指していると読むべきでしょう。メディアでの露出、世論調査の出し方、SNSでの情報拡散、教育現場での言説――これらを総動員して「反対の方が変だ」という雰囲気を作る。それが政治的に言う「環境づくり」です。
こうした空気ができてしまえば、あとは“投票に来る人”さえ確保すればいい。沈黙している人たちを説得するより、動員できる支持層を固めるほうがコスパがいい。これが現代型の世論戦の考え方です。
つまり、民主主義の手続きをまわしながら、実際には「結果の出しやすい土俵」を先につくってしまう。これがいま進んでいる「管理された民意」のかたちです。
■ クラウドワークスなどの“動員インフラ”
ここで気になるのが、同じ時期に起きた別の動きです。2025年9月3日、クラウドワークス代表の吉田浩一郎氏が内閣府から紺綬褒章を授与されています。名目は「公益財団法人 国際文化会館」への寄付に対する顕彰です。
クラウドワークスは、500万人以上の登録者を抱える国内最大級のクラウドソーシングサービスです。政府・自治体・官公庁・広告代理店からの案件も多く、PR・デザイン・SNS運用といった「情報流通の作業」を大量に受けられる構造を持っています。これは裏を返せば、ネット上で人を一斉に動かせる“民間の動員プラットフォーム”だということです。
そのトップが、ちょうど国民投票・憲法改正を政府が前に出し始めたタイミングで、政府から「社会貢献」として顕彰される。これを「まったくの偶然」と見るより、「官民が同じ方向を向いているというサイン」と受け取る人がいてもおかしくありません。
紺綬褒章自体は制度として正当なものです。ただし、寄付先の国際文化会館は外務省OBや財界人、国際機関関係者が集まる外交・文化ネットワークの中核でもあります。つまりこれは、寄付を通じて「政官財ネットワークへのアクセス」を得る動きとしても読めるのです。
国民投票は制度的に“情報戦”です。日本の国民投票法には広告規制がほぼなく、資金力のある側がオンライン広告・SNS・アウトソーシングを使って世論をつくれます。そうした時に、安価で大量に「人手をネット上で動かせる」プラットフォームの価値は一気に上がります。将来的に世論操作の実働部隊として使われるリスクは、十分に考えられるところです。
本稿は、吉田浩一郎氏またはクラウドワークス社が国民投票や世論工作に関与したと主張するものではありません。
紺綬褒章の授与時期が政治的動きと近かったことを踏まえ、制度と社会構造の「タイミングの符合」を分析的に論じています。
■ “空気づくり”という名の政治技術
政治は直接票を動かさなくても、空気を動かすことはできます。そして現代では、その空気を動かすための官民の回路がすでに存在しています。
「賛成が常識」「反対は時代遅れ」「とりあえずやってみよう」――こうしたムードを先に社会に流し込めば、国民投票は“決める場”ではなく“確認する場”に変わります。人は、すでに決まっていると感じたほうに流れるからです。
この“空気づくり”の背後には、政治家だけでなく、メディア、広告代理店、デジタルプラットフォーム、そしてクラウドソーシングのような新しい動員インフラがあります。国家はもはや「命令」ではなく「共感」と「同調」で社会を動かす。そのための準備が、今しずかに進んでいるのだと思います。
この原稿を書きながら、ずっと胸の奥がざらついていました。
「国民に問う」と言われると、私たちはそれだけで正しい手続きのように思ってしまいます。でも、その制度の中に“沈黙を切り捨てる”設計が最初から入っているなら、それは本当に民意を測るしくみと言えるのでしょうか。
しかも、やさしい言葉で、静かに、何も争いがないような顔をして進んでいく。これがいちばん怖いところです。
民主主義の危機は、劇的な独裁の登場ではなく、「考えなくてもいい空気」が広がったときに訪れます。沈黙している人の中にも意見はあるはずで、その声を最初から“なかったこと”にする制度が広がるのなら、私はやはり書いておきたいと思いました。
――静かな声を見失わないでいたい。そう思って、この稿を残します。
海外ニュース翻訳情報局 編集長 樺島万里子
Constitutional Referendum in Japan: Public Will or Mobilization?
On November 4, Prime Minister Sanae Takaichi stated in the Diet that she would “create an environment” to put constitutional revision to a national referendum as soon as possible. On the surface, this sounds like a democratic commitment. But once we look at how Japan’s referendum system actually works, a different picture emerges.
■ The Built-in Bias
Japan’s referendum is decided not by a majority of all eligible voters, but by a majority of those who actually cast a ballot. This “absolute voter” system means that abstentions simply vanish from the count. The lower the turnout, the easier it becomes for an organized camp to win.
■ Managed Consensus
What the government calls “creating an environment” often means manufacturing a social climate in which support for revision appears normal. Media exposure, polling, and social media messaging can all be aligned to make “yes” look like the mainstream choice. In such a climate, the referendum is no longer deliberation, but confirmation.
■ CrowdWorks as Digital Mobilization
It is in this context that the September 3, 2025 awarding of the Dark Blue Ribbon Medal to CrowdWorks CEO Koichiro Yoshida becomes interesting. CrowdWorks is a massive platform that can mobilize millions of online workers for PR, design, and social-media tasks — including government-related projects. In a system where online narratives matter more than turnout, such a platform can function as a de facto mobilization infrastructure.
■ Political Signaling
The medal was formally for a donation to the International House of Japan, but the timing overlaps with the government’s renewed push for constitutional revision. Read together, it can be taken as a quiet signal of alignment between the state and the private infrastructure that can help shape public opinion.
■ Conclusion
Japan’s constitutional referendum is presented as the purest form of democracy. Yet, in practice, it can operate as a system for designing consent — especially when abstentions are structurally ignored and when digital labor can be mobilized to steer the narrative. The real question, then, is not “What do the people want?” but “Who gets to define the atmosphere in which the people decide?”